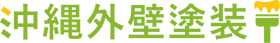外壁・屋根塗装に使用される塗料の種類(グレード)や特徴
塗料選びは、外壁塗装の料金や耐久年数を決めるので重要です。塗料についての知識がないと、業者が提案してきた塗料が本当にいい塗料なのか?が判断ができません。そのため、塗料のグレードごと(シリコンやフッ素など)の耐久年数や価格帯を理解することをオススメします。
但し、どんなに良い塗料を使っても、業者が手抜きなくしっかりと施工しなければ、塗料が持つ耐久年数を発揮できない点だけは注意が必要です。
塗料の種類別の単価と耐久性
下記の単価は3回塗り(シーラー等+中塗り+上塗り)の合計単価になります。怪しい業者だと、3回塗りで2,300~3,000円のシリコンを、1回塗り辺り2,300~3,000円の単価で提案してくることがあるので注意してください。
単価や耐久年数に幅があるのは、同じシリコン塗料でもその中でグレードの違いがあったり、各メーカーによっても違いがあるからです。耐久年数は、あくまでも期待できる耐久年数で、塗料(塗膜)がしっかりと機能することができる年数です。絶対にこの年数まで持つわけではありません。
メーカー発表の耐用年数はあくまで室内でのテスト結果
よく「必ずメーカーのカタログに書いてある耐久年数はもつんですよね?」と言われますが、それは違います。
メーカーが自社の塗料の耐久年数のテストをする場合は、促進耐候性試験と呼ばれる人工の太陽光を浴びせ室内で試験します。
この試験は、自然の太陽光よりも強い光を当てるため、早く数年後の劣化状態を確認できます。試験結果はJIS A6909耐候形1~3種というようにJIS規格で定められています。
但し、あくまでも室内の試験なので、塩害や凍害、雨などの劣化を早くする要素が含まれていないため、あくまでもテスト上の耐久年数になってしまいます。そのため、実際に住宅に塗ると思ったより耐久しなかったということがあります。
本来なら住宅と同じ環境で外でテストする暴露試験が望ましいのですが、結果が出るまで時間がかかるため、各メーカーが促進耐候性試験を採用しています。
促進耐候性試験には、
・キセノンランプ促進耐候性試験(カタログ略語XWOM)
・サンシャインウェザーメーター促進耐候性試験(カタログ略語SWOM
などがあり、今はキセノンランプ促進耐候性試験が多いです。
宮古島などの日光が強いところでテストする暴露試験などもありますが、コストを考えると促進耐候性試験が採用されています。
イメージとしては、自動車の燃費試験と似ているかもしれません。メーカーのカタログに書いてあっても、実際に乗るとそこまで燃費が良くないという経験をしたことがある人も多いと思います…。
塗料の成分を解説 ~合成樹脂は塗料の耐久年数を決める重要な要素~
塗料とは、顔料、添加剤、合成樹脂、これらの3の成分を混ぜ合わせたものを言います。各成分は以下のような役割があります。
・顔料:色やツヤを決める役割
・添加剤:塗膜を均等にする塗膜に特別な機能を持たせる役割
・合成樹脂:耐久性などの保護機能の役割
合成樹脂は、耐久年数に関わるので、塗料を選ぶ中で一番重要です。種類は4種類あり、アクリル合成樹脂、ウレタン合成樹脂、シリコン合成樹脂、フッ素合成樹脂に分かれます。
それぞれの合成樹脂は、油性(強溶剤、弱溶剤)、水性に分類されます。水性は、1液タイプと2液タイプの2つに分かれます。
もしかすると、「シリコン塗料が主流」「フッ素は高級な塗料」というようなことを聞いたことがあるかもしれませんが、これらは合成樹脂のことを言っています。